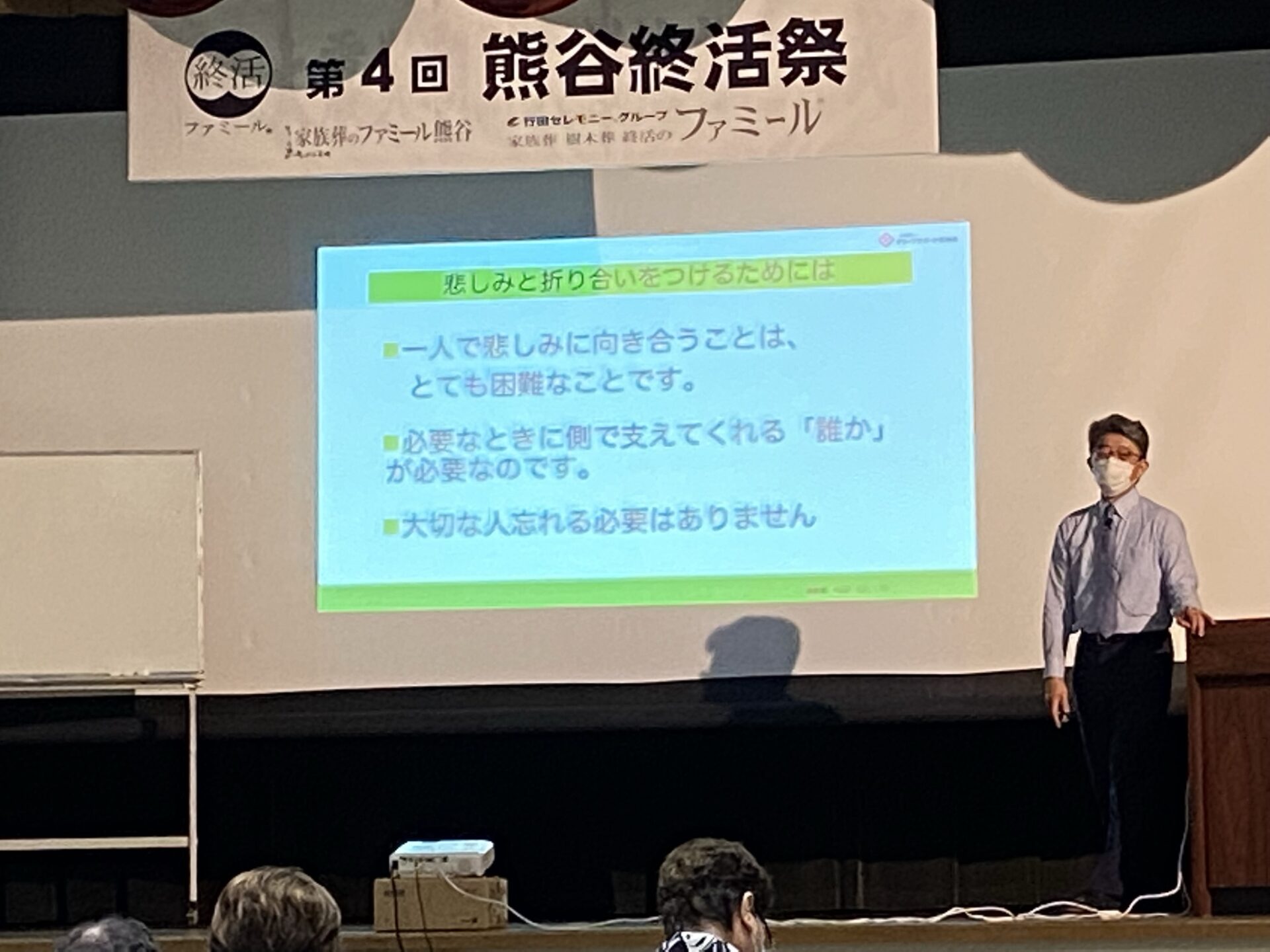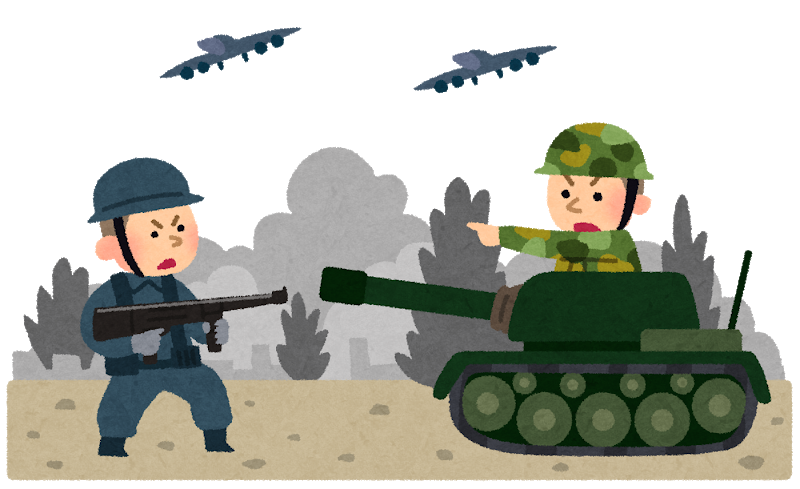日本におけるエンバーマーの第一人者でありながら、グリーフサポートの協会を立上げ、遺族への支援の輪を広めている橋爪謙一郎氏の公開講演会を主催した。(第4回熊谷終活祭)
橋爪氏の活躍は、葬儀業界では知らない人はいない。
先日も晴海での展示会(エンディング産業展)でも登壇し、コロナによって変わった顧客像について語ってくれたばかりだ。
ただ今回は、いつもの業者向けの専門的な講演とは違い、一般の方に向けた企画なので、違った方向から拝聴できると期待をしていた。
ちょうど関東は梅雨に入ったばかりで、前日の夜から降り出した雨が、橋爪夫妻が熊谷駅に到着した朝まで続いていた。
厚い鉄骨とタイルで囲まれた駅の構内は、湿気で重くベタベタした空気で充満していた。
「熊谷は“暑い〟というイメージなんですがねえ」
北海道生まれの橋爪氏は梅雨は苦手らしく、失笑をこぼしていた。
この雨のせいもあるかもしれないが、10時30分から開会時、会場の席には空席が目立った。
しかし拝聴した方は、靴を濡らしても足を運んだことが無駄ではなかったと思うくらい、橋爪氏の講演は分かりやすく、感動を与えてくれるものであった。
講演の様子は氏の了解を得て当社の youtube(行田セレモニーグループチャンネル)にアップしているので、ぜひご覧頂きたい。
ここでは送迎の途中で交わした個人的な会話について触れる。
氏はこの業界に「お金儲けが上手な人」が増えていることに憂いていた。
もちろんお金を儲けることが悪いことじゃない。
しかしビジネスゲームのように、葬儀会社を立上げ、売り逃げるオーナーが目立つようになってきた。
経営者が利だけを求めるものだから、現場の社員も自分たちの商品だけを売りつける営業主義になっている。
遺族の声に耳を傾けることなく、葬儀の仕事を作業として担うだけだから、ますます形骸化が進み、遺族の心を整えるという本来の葬儀の意義が喪いつつある。
エンバーマーとして多くの遺体に触れ、悲しむ遺族の心に寄り添ってきた氏だからこそ、私たち葬儀の仕事に携わる者への警鐘は重く響く。
そういえば、ティアの富安社長や、清月記の菅原社長も同じようなことを言っていた。
いずれも現場のたたき上げの方ばかりで、大切な人を喪った方たちの悲嘆を身近に見て接してきた人たちだ。
彼らは知っているののだろう。葬儀の仕事の中には現場を知らない人たちには理解できない〝聖域”があることを。
悲しみに一人で向かうことは困難である。だからこそ人が寄り添う「葬儀」は必要なのだ。簡単な声がけだけでもいい。遺族が知らない思い出話でもいい。そして堂々巡りになっても遺族の話に耳を傾けてあげてほしい。そのような些細なことが遺族の支えになる。もちろん葬儀社の社員でもそのようなことはできる。かつてその役割を担ってきた宗教者が少なくなってきた今、葬儀社のポテンシャルは高い。
コロナ禍で経営環境が厳しいなか、お客様に支えられ残っていくのは、そのような葬儀社しかいないだろうという橋爪氏の言葉が心に残った。
【社長コラム177】コロナ禍での葬儀社の役割~エンバーマーかく語りき~